読み物
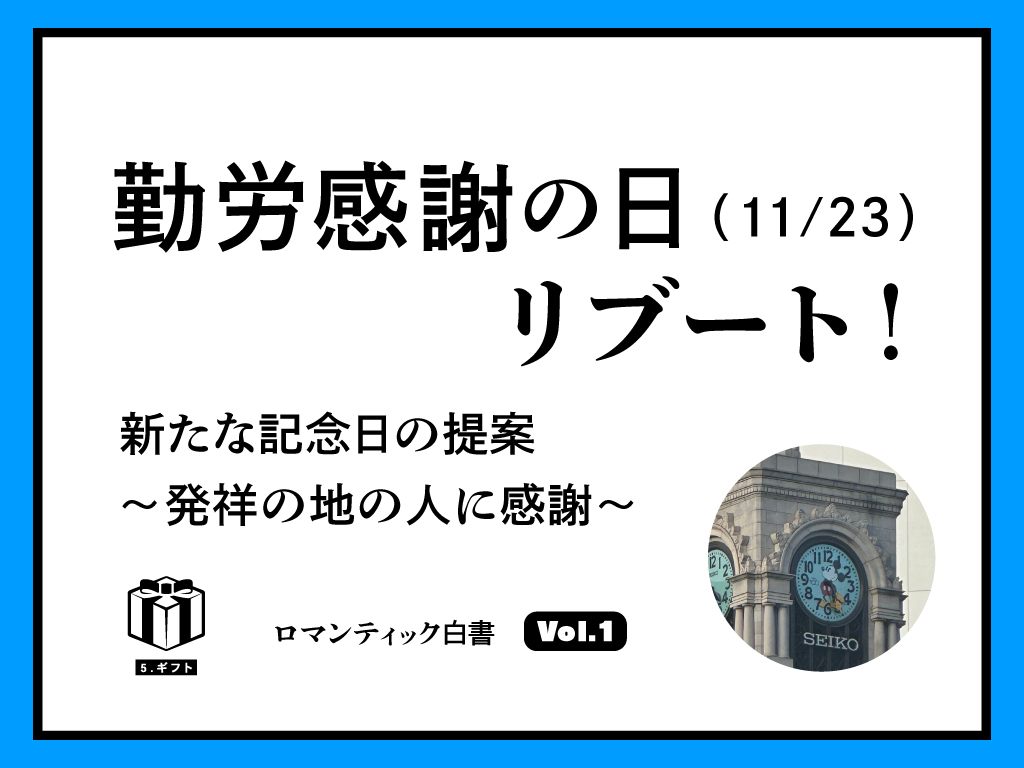

編集会議で「もうすぐ勤労感謝の日だね」という話題に。
仕事や労働を通して家庭や社会を支えてくれる方々に、感謝を伝える日――
せっかくなら、「いつも頑張っている誰かに感謝を届けよう」ということに。
日本ロマンチスト協会では、大切なパートナーとの関係を育むため、
日常的に“思いやり”や“感謝”を伝えることを大切にしている。
さまざまなアイデアが出る中で、
「特定の誰か」ではなく、
「記事を読んでくださる皆さんにも楽しんでいただける話題」を、
感謝の気持ちを込めて、お届けすることにした。

そもそも、勤労感謝の日とは何なのか?
そのルーツは、その年の収穫に感謝する「新嘗祭(にいなめさい)」という、天皇が国家と国民の安寧と繁栄を祈る儀式にある。
新嘗祭は第35代・皇極天皇(642~644)の時代に始まったとされ、1873年に11月23日が祝祭日に指定された。神からの恵みと、多くの人々の働きによって、もたらされた豊作に感謝する日とされていた。
その後、第二次大戦後の1947年にGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により皇室祭祀令が廃止されるが、翌1948年、「国民の祝日に関する法律」の制定により、「勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう日」として「勤労感謝の日」に改称された。

「勤労感謝の日」にあたり、編集部から皆さんに何をお贈りすれば良いか? 考えた私たちは「マインドフルめし」から着想を得て、身近にある”発祥の地”を調べてみることにした。
物事の発祥には、もちろん、さまざまなカテゴリーやジャンルがあるが、注目したのはグルメ。編集部で飲食店の「元祖」を調べたところ、横浜、日本橋、銀座、浅草に多くのお店が集まっていることがわかった。これらの繁華街には、歴史や文化が息づき、魅力ある”発祥の地”が点在している。
それぞれの街で特集が組めそうだが、今回はNHKの連続テレビ小説「あんぱん」のモデル・やなせたかしが魅了され、筆者の馴染みの街でもある”銀座”の発祥の地を紹介したい。
今回、紹介するお店はいずれも、掲載日時点で営業している創業100年を超える老舗の元祖を筆者の独断で厳選した。
まず、お店を紹介する前に、多くの元祖が誕生した明治(1868~1912年)・大正(1912~1926年)期を中心に銀座の歴史をふり返ってみたい。

銀座は三度の大被害を被っている。明治の大火(1872年)、関東大震災(1923年)、そして第二次大戦の銀座空襲(1945年)――を乗り越えながら、文化と流行の発信地として歩み続けてきた稀有な街だ。
まず、明治の大火を教訓にモダンな煉瓦街へと生まれ変わり、さらに、わずか半年後には日本初の鉄道(新橋―横浜間)が開通。
特筆すべきは、関東大震災後、わずか二ヶ月で商売を再開。銀座の人たちの粘り強さと、矜持が感じられる出来事である。これが、さまざまな「発祥の地」が集まるゆえんだろう。
やなせたかしは自伝『アンパンマンの遺書』に、上京した当時(1937年)の銀座を以下のように記している。
”田舎から出てきてお国なまりのぬけない少年は、
啞然、茫然、夢見ごこちで銀座の舗道を歩いた。
この街にぼくの青春はあったし、
学校よりもはるかに多くのことを学んだ。
サンドイッチマンからも、映画館のモギリ嬢からも、
喫茶店のウェイトレスからも学んだ。
みんなぼくの先生だった”
『アンパンマンの遺書』「起の巻 アンパンマン以前史ー銀座学校」岩波現代文庫、2013年
今も銀座には、この“息づかい”が感じられる。
創業100年を超え、伝統を守り、時代に寄り添い続けてきた老舗の逸品を紹介したい。
さっそく、“銀座の発祥の地”をめぐる小さな旅に出てみよう。
まず、当協会の象徴“偏愛の気配をまとうTシャツ”「IDENTI-T(アイデンティT)」のデザインにちなんで、クリームソーダから紹介したい。
たんじょう:1902(明治35)年|123年前
がんそめにゅー:クリームソーダ

1872年、日本初の調剤薬局として誕生した資生堂は、1902年に「ソーダ水」と「アイスクリーム」の販売を開始。やがて、両者を組み合わせた“アイスクリームソーダ”を考案し、これがクリームソーダの元祖とされる。
1922年当時、大卒初任給が50円(※)の時代に「アイスクリームソーダ」は40銭で提供。まさに高級メニューだった。
当時の新橋芸者衆――いわば“明治のインフルエンサー”が愛したことで、その人気は一気に広まり、名物に。
現在は3階「サロン・ド・カフェ」で楽しめる。
週末は行列必至なので、11時の開店直後の来店がおすすめ。
たんじょう:1874(明治7)年|123年前
がんそめにゅー:あんぱん、ジャムパン

連続テレビ小説『あんぱん』に登場するパン屋のモデルにもなった木村屋。初代・木村安兵衛は、公務員から50歳でパン屋「文英堂」を創業し(1869年)、息子の英三郎とともに日本人の口に合うパンづくりを追及。酒種酵母による柔らかな生地を生み出し、1874年に「酒種あんぱん」が誕生。同時期に、新橋から銀座四丁目へ進出。
侍従・山岡鉄舟の勧めで明治天皇にあんぱんが献上され、たちまち評判に。やがて明治初期の流行語「文明開化の7つ道具」にも挙げられるほどの人気となった。
さらに、1900年には三代目・儀四郎があんずジャム入りのパンを発売し、日本初の「ジャムパン」が誕生。木村屋は激動の時代にも負けず、常に新しい味を創り出してきた。
たんじょう:1902(昭和7)年|93年前
がんそめにゅー:若鶏の唐揚げ

三笠会館の始まりは、ちょうど100年前に創業した歌舞伎座前のかき氷店「氷水屋三笠」。その後、1902年、昭和恐慌のさなかに銀座一丁目へ支店を開くも経営難に陥る。しかし、中国料理の技法をヒントに「若鶏の唐揚げ」を生み出し、見事に危機を脱した。
実は、漫画家・手塚治虫は、三笠会館の大ファン。後輩の松本零士が上京した際には、水野英子を伴って店を案内。後に、松本は唐揚げを食べた感想を「料理にあんなにうまいものがあるんだろうかと(笑)」と語っている。
(講談社版手塚全集『手塚治虫対談集2』/初出:『Oh!漫画』1982年・晶文社)
この伝統の味は、「イタリアンバール LA VIOLA」で楽しめる。筆者のオススメは、“ビール(特にギネス)×唐揚げ”という最強コンビだ。
たんじょう:1894(明治27)年|131年前
がんそめにゅー:フルーツパーラー、フルーツポンチ

千疋屋総本店の番頭・齋藤義政が、27歳の若さで暖簾分けを許され、1894年に銀座八丁目に果物専門店「新橋千疋屋」を創業。二代目の齋藤甚作は、家業発展に尽力し、1913年に日本初のフルーツパーラー「果物食堂フルーツパーラー」を開業した。
甚作は生粋の果物好きで、研究熱心。海外にも足繁く通い、果物屋の客足が減る秋冬の新たな目玉商品として、1923年に「フルーツポンチ」を発売した。果物そのもののおいしさを伝えるため、あえて手を加えすぎないシンプルな作りが特徴だ。筆者のオススメは、季節ごとに厳選農家から届く旬の果物を使ったパフェと一緒に味わいたい。
たんじょう:1899(明治32)年|126年前
がんそめにゅー:日本初のビアホール

1887年に日本麦酒醸造会社が設立され、目黒・三田に醸造場が完成。1890年には「恵比寿ビール」が発売され、偽物が出回るほどの人気に。お中元に贈られる文化が定着したのもこの頃。
工場直送の新鮮な生ビールを届けたいとの思いで、1899年に日本初のビヤホール「恵比壽ビヤホール」が銀座に誕生。1日平均800人が訪れる盛況ぶりだった。現在は「ビヤホールライオン銀座七丁目店」として営業しており、建物全体が国登録有形文化財だ。
余談だが、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、小泉八雲が松江でビールを所望するシーンがコミカルに描かれ話題となった。発売間もない「恵比寿ビール」を味わったかもしれない・・・
“⼀度注ぎ”によるまろやかな生ビールは、苦手な人でも飲みやすいと評判。1階は予約不可のため、平日もしくは週末の16時台の入店が狙い目。
銀座の老舗の多くは三度の災害を乗り越えながらも、伝統を守りつつ創意工夫を続けてきた。当時のレシピのまま提供するのではなく、時代に合わせて何度も変化を重ねてきたこともポイントだ。店主たちが日々お客様の声に丁寧に向き合う姿勢が、銀座の多彩な文化を支え続けている。
敷居が高そうに思える銀座だが、老舗の店には下町の人情も息づく。時代に合わせた味や工夫に触れながら、銀座の歴史と文化を感じる、気軽なショートトリップに感謝の気持ちを伝えたい人と一緒に出かけてみよう。
記事:研究員 佐々木倫子
(※)週刊朝日 編. 値段史年表 : 明治・大正・昭和, 朝日新聞社, 1988.6. 4-02-255868-7, 10.11501/13873105.
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000001930338
【主な参考資料・出典】 2025年11月7日閲覧
※本記事は上記資料に加え、関連メディアの公開情報を対象としたデスクリサーチ(編集者調べ)に基づき作成しています。
なお、記事の読みやすさを考え、記事内では人物の敬称を略して記載しています。
© NIPPON ROMANTICIST ASSOCIATION All rights reserved.