読み物
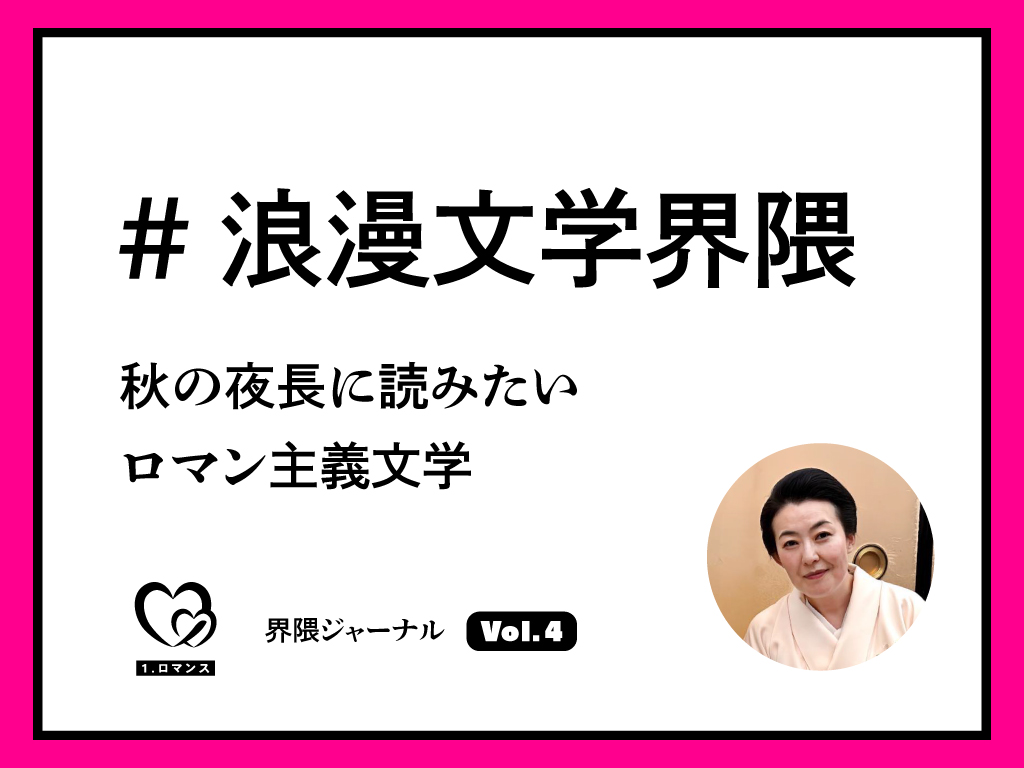
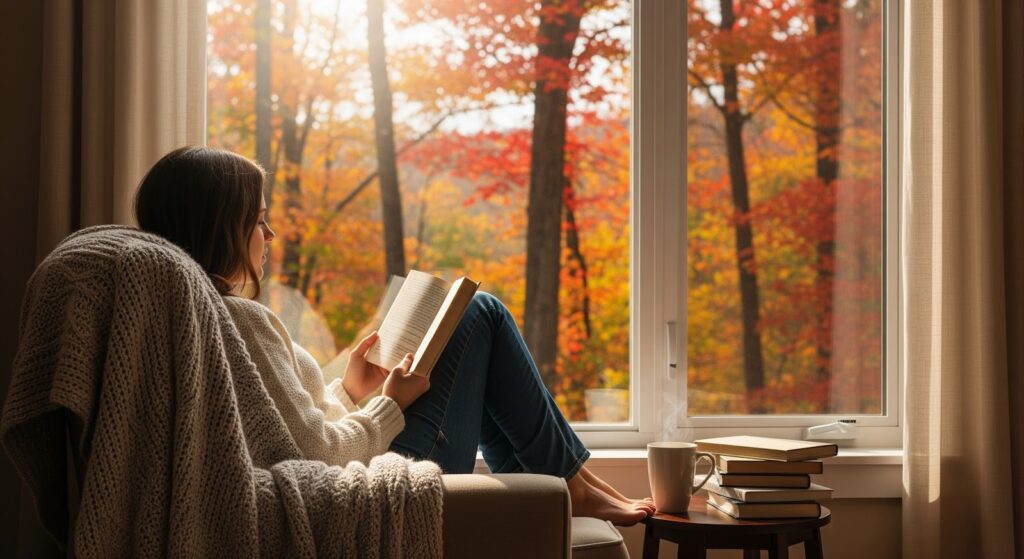
この時期によく耳にする言葉のひとつに「読書の秋」がある。
私も多くの人と同じように、幼いころから何度も耳にし、自然に受け入れてきた。本は私にとって無二の親友であり、ときに師であり、寄り添ってくれる存在でもある。女優の芦田愛菜が”活字中毒”として知られているが、私自身も少なからずその傾向があると思う。
最近ふと、「なぜ“読書の秋”と言うのだろう?」と気になって調べてみた。どうやらその起源は漢詩と深く関わり、さらにロマン主義にも通じているらしい。これを知ったとき、少しロマンを感じたので紹介してみたい。
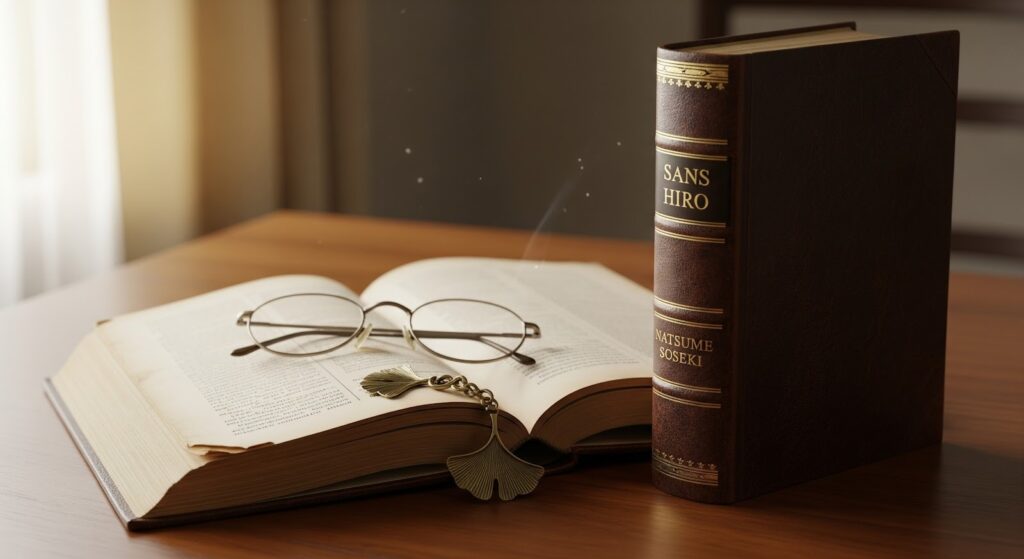
日本で「読書の秋」という言葉が使われるようになったのは、明治時代後期にさかのぼる。そのきっかけは、夏目漱石が1908年9月から12月にかけて朝日新聞に連載した青春小説「三四郎」の中にあった。
主人公・三四郎の友人、与次郎が東京での生活に慣れ、中国の漢語「燈火親しむべし(涼しい秋の夜長は、灯火の下で読書を楽しむのに適している)」と、インテリぶって嬉々として使う様子を、漱石は愛のある皮肉を込めて表し、日本に定着させたのだ。
”そのうち与次郎の尻が次第に落ち付いて来て、燈火親しむべしなどという漢語さえ借用して嬉(うれ)しがるようになった。話題は端(はし)なく広田先生の上に落ちた。”
夏目漱石『三四郎』(第三十四回)四の六(朝日新聞、2014年11月19日 5時00分)
余談だが、「三四郎」には「ストレイ・シープ(迷える子)」という象徴的な言葉も登場する。米津玄師が2020年に発売したアルバム「STRAY SHEEP」発売当初、「漱石へのオマージュでは?」とファンの間で話題になったほどだ。無類の本好きとして知られる、米津の一面が垣間見えるエピソードでもある。

この「燈火親しむべし」という言葉は、中国・唐代中期に活躍した士大夫(したいふ=
上級知識人)の韓愈(かんゆ)が詠んだ漢詩「符読書城南詩(ふしょ じょうなんに よむ)『全唐詩』341巻)」の一説に由来する。
灯火稍可亲(とうか ようやく 親しむべく),簡編可卷舒(かんぺん けんじょすべし)。
書の秋の由来とは?「好きな本診断」と「読書ノート」で読書を楽しもう!(日本速読解力協会)
意味は「秋の夜、灯りの下で読書をするのにちょうどよい季節となり、書物を広げてゆったりと読むことができる」。当時18歳だった息子・符に向けて、”学びは人生を豊かにする”という父からの訓示として詠まれた詩だった。
ちなみに、韓愈の著作「朱文公校昌黎(しゅぶんこうこうしょうれい)先生集」は、今年4月にテレビ東京系列の「開運!なんでも鑑定団」で歴代4位となる3億円の鑑定額を記録した。所蔵する銚子・円福寺では、5月に限定公開されたという。

なぜ夏目漱石は中国・唐代中期に活躍した文人の言葉を引用したのだろうか?
儒学や漢学は江戸時代に知識人のたしなみとして確立し、明治時代に入っても、その流れは続いた。旧制中学や高校では男子の教養の一環として漢文の学習が必須で、新聞には漢詩の投稿欄があり、漢詩の投稿雑誌も20種類以上刊行されていたという。
そうした世相の中で、夏目漱石も幼いころから漢詩に親しみ、将来の職業にしようと考えた時期があったようだ。やがて、成立学舎で英語の才能を発揮し、漢詩を生業とすることはなかったが、生涯にわたって漢詩を作り続けた。
夏目漱石のほか、森鷗外や永井荷風、俳人の正岡子規もまた、漢詩に深い造詣を持つ文学者だった。彼らの詩は「漢詩百首 日本語を豊かに」(高橋睦郎 著・中公新書)にも収録されており、その作品にも、漢文学の思想が色濃く反映されている。
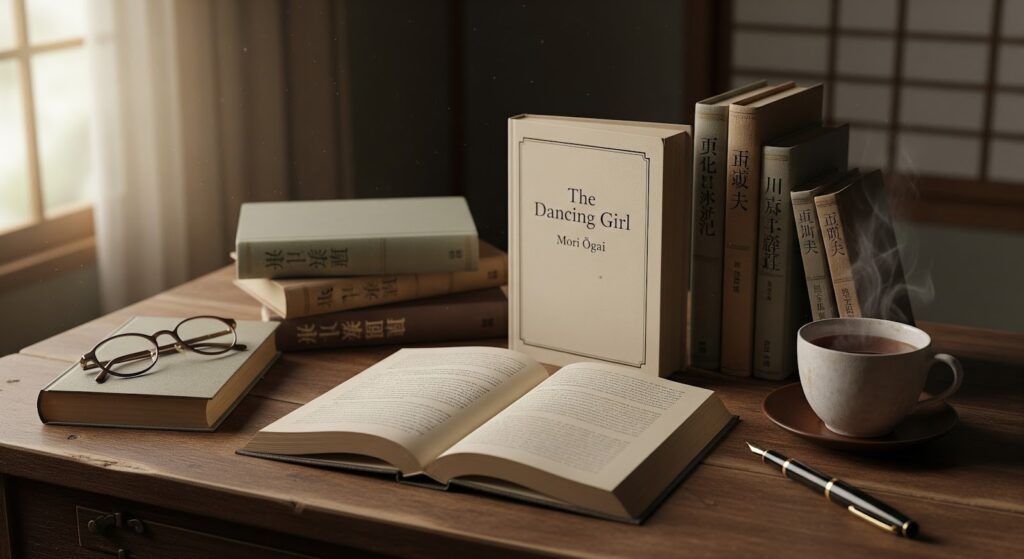
明治初期、文明開化によって西洋思想がもたらされると、ゲーテやバイロン、ヴィクトル・ユーゴーなど、西欧ロマン主義に感化された作家たちが誕生。日本的な感性と融合させることで、日本独自のロマン主義を生み出していった。
その先駆けは、森鴎外が1980年に雑誌「国民之友」で発表した「舞姫」だ。ドイツ留学中の青年・太田豊太郎が、舞姫エリスとの恋愛と祖国への忠誠の狭間で苦悩する姿を描いた作品で、森鴎外自身の体験が色濃く投影されているといわれている。
「舞姫」もまた、漢語混じりの文語体で書かれた作品であり、鴎外が漢語を自在に操る達人であったことが伺えるのだ。
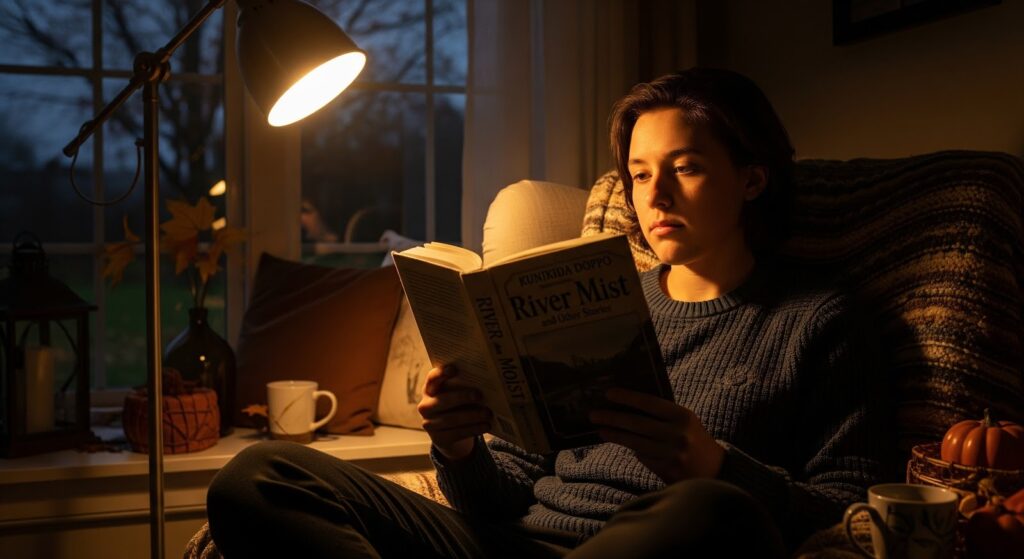
日本の代表的なロマン主義作家が残した作品の中には、今でも読み継がれているものが多い。ここでは、代表的な作品をいくつか紹介したい。
1897年に春陽堂から刊行された処女詩集。日本の近代詩において、感情と自然の融合という、新たな表現を切り開いた革新的な1冊。島崎は姪との恋愛で社会的非難を浴びるなど、その人生もまたドラマチック。
1901年刊行の処女歌集。人気歌人・与謝野鉄幹への恋をきっかけに、不倫・略奪婚、そして恋の歌へ。奔放すぎる愛の表現でバッシングを受けつつも、11人の子を育てた伝説の“肝っ玉母ちゃん歌人”。
五千円札の肖像画でおなじみの樋口一様が、1895年1月から1年間、雑誌「文学界」に連載した中編小説。明治時代の下町・吉原を舞台に、思春期の少年少女の淡い恋と成長を描く。一葉は苦しい生活の中でも小説家として成功を目指し、自立した生き方を貫いた。
1898年に雑誌「国民之友」に発表された随筆風短編。東京近郊の武蔵野地域を舞台に、日本語の美しいリズムで自然の美と、人生のはかなさや寂しさを情緒的に描いた。ちなみに、NHK朝ドラ「あんぱん」で主人公の亡き夫を演じた俳優・中島歩は、独歩の玄孫(ひ孫の子)。
ロマン文学は、今からおよそ130年前に花開き、今もなお多くの人に読み継がれている。個人の内面に迫り、心の機微を繊細に描く作品が多いのも特徴だ。
暑さがようやく落ち着き、夜が長く感じられる秋――ロマン文学を手に取り、静かに自分の人生を見つめ直してみてはどうだろうか。
きっと、実りの秋がこれからの人生に、いっそうの深みを与えてくれることだろう。
記事:研究員 佐々木倫子
【主な参考資料・出典】 2025年10月6日閲覧
※本記事は上記資料に加え、関連メディアの公開情報を対象としたデスクリサーチ(編集者調べ)に基づき作成しています。
なお、記事の読みやすさを考え、記事内では人物の敬称を略して記載しています。
© NIPPON ROMANTICIST ASSOCIATION All rights reserved.